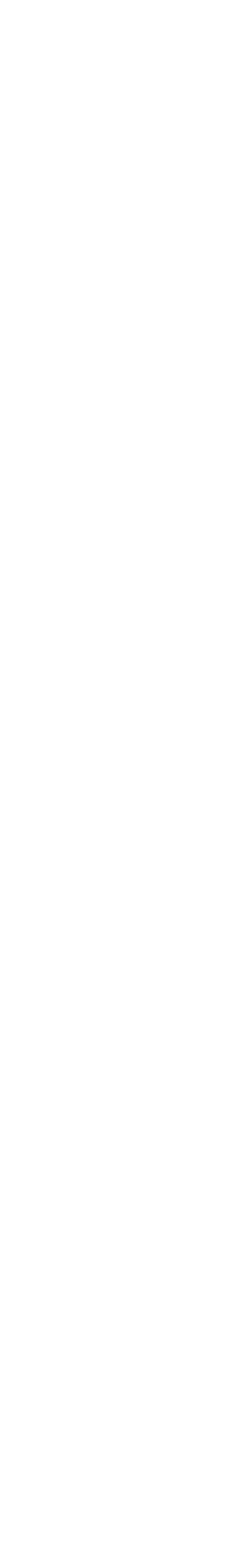崩壊の箱:いたずら好きの子供たちへの戒め – 「スカルの季節」ストーリー最終話
By Jeffrey Campbell


昔あるところに、二人のいじわるな顔をした少女らがいました。二人に会ったことがある人は皆、その手に負えないふるまいについて話し、二人と話したことがある人は皆、二人が悪い子であることを知っていました。
そう、二人は単にいじわるな顔をしているだけではなかったのです。二人はいじわるで、行儀が悪く、傲慢で、みんなから嫌われていました。仕事が大嫌いで、街の規則を守っている市民に対して考え得る限りのいじわるないたずらをすることで有名でした。二人がこうなったのは、生まれたばかりの頃に街の裏通りに捨てられて、善悪を教えてくれる親がいなかったからなのだと考えられていました。
しかしその不幸な身の上にもかかわらず、二人のあまりの態度の悪さに、この子たちを可哀想だと考えるのは本当に寛大な人たちだけなのでした。
そんな時代でした。
ある日、二人は自分たちが「お楽しみ」とこっそり呼んでいる悪いいたずらをたくさん仕掛けました。
魚屋の商品にヴェスニドの粉を振りかけて、買った魚を食べた人たちの目を一日中見えなくしたり。赤ちゃんワイバーンをいじめてサトーミに放し、そこで調査をしていたサイファーの校長に噛み傷と火傷を負わせたり。ジャベリン工房から鋼鉄のベアリングを盗んで市場の店の周りにばらまき、商人や常連客にけがをさせたり。さらには、センチネル・キャプテンの忠実な猟犬を誘拐して荒地の近くを「散歩」させ、野生のコロックスにあわや踏みつぶされるという目に合わせたりもしました。
二人のいじわる顔の少女らは、こういったお楽しみが大好きでした。
「私たち、この街いちばんの天才ね!そう思わない?」一人が言います。
もう一人が答えます。「本当ね。ただ天才なだけじゃないわ。いちばんかわいいのも私たちよ!」
そして二人は獣のような嫌な声を立てて笑いました。近くにいた焼物師はそれに驚いてうわぐすりをこぼし、雑貨屋から新たに買ってこなければなりませんでした。
しかしこの日はいつもとは違いました。センチネル・キャプテンが二人を現場で押さえ、罰を与えるために捕まえたのです。包帯を巻かれた痛々しい姿の猟犬が見張り、犯人である二人が近くのさらし台に固定されているなか、センチネル・キャプテンは被害者の話を聞いてその訴えについてよく考えました。
「いちばん深い監獄に入れてやれ!」まだ目をこすりながらそう叫ぶのは魚屋です。
「異端者の焼き印を押してやれ!」金切り声でそう叫ぶのは市場の責任者です。松葉づえをついて、脚を引きずっています。
「悪ガキにはむち打ち30回だ!」おでこの咬み跡を指さしながら、サイファーの校長がわめきます。
「あなたがやる? 校長先生?」片方の少女は身体をよじってズボンを脱ぐと、その青白いお尻を集まった人々に見せながらそう大声で言いました。
群衆が前方へと押し寄せます。彼らの抱く憎しみはもうランプオイルのような熱さです。「被害者のためにお願いします、キャプテン」彼らは叫びます。「あなたの犬を見てください!」
しかしキャプテンはただ腕を組んでいるだけ。あらゆる欠点があるにもかかわらず、キャプテンはこのいたずら娘たちのことが好きなのでした。そのため、キャプテンは法律にのっとって、このいじわる顔の少女らに街のフリーランサー保管庫での二週間の労働を言い渡しました。
二人を保管庫責任者に引き渡すとき、キャプテンは言いました。「あなたたちが本当はいい子だって知ってるわ。
そのいじわるな心の中に、ぼんやりと光っているのが分かる。発明のひらめきがね。みんなに必要とされるものよ」キャプテンは膝をつくと、二人のいじわるな顔を見つめました。「だから約束してちょうだい。自分たちの中の光と向き合うって。そうすれば他の人たちにも、あなたたちの本当の姿が見えるかもしれない」
「約束する」と二人は嘘をつきました。
保管庫の責任者はその夜、二人に保管庫の奥を掃くように言いつけて帰ってしまったため、二人の悪い心はみるみる息を吹き返しました。分類が終わっていない回収品をあさったり。使われなくなったジャベリンで着せ替えごっこをしたり。空の迫撃砲を投げて遊び、信管を外した地雷の上で踊ったり。押収された書類と鉛筆書きの汚れた判じ物を、未翻訳の研究書の中でごちゃごちゃにしたり。使用済みのエンバーの粉を手に取って空中に投げ、銀色の雲の中で電光がフラクタル模様を映し出すのに仰天したり。
そして、二人はその箱を見つけたのです。
それは地味な見た目の箱で、フリーランサーの回収品を鑑定した若手サイファーによって見落とされたことは明らかでした。灰色の金属の面が12面あり、触ると冷たく滑らかで、端に小さな穴が一つ開いています。いじっても、何も起こりませんでした。
…はじめは。
いい子たちは、このような物体に触っていいのはアルカニストやフリーランサー、あるいはその他の専門家だけであると知っています。もし触ると、街の壁の中でこれまで起こったこともないような危険を呼び寄せてしまうからです。そのため、左手の指3本を切り落とすという最も重い罰を科すことで、センチネルは未知の物に触ることを戒めていました。
そんな時代でした。
しかし、善悪を教えてくれる親がいなかったいじわる顔の少女らは、規則を守ったりなどしません。ですから、好奇心が強く創造性に富んだ二人は、この箱の機能を解明することにしたのです。
まもなく、二人はその物体のパネルを見えない平面に沿って滑らせることができると発見しました。一度滑らせるごとに、箱は言葉では言い表せないような方法でその形を変えていきます。12面が16面になり、16面が23面になり、23面が18面になりました。そして形が変わるたびに、まばゆい光が小さな穴から放たれました。その光は炎のように照り輝き、氷のようにきらめいています。
その奇妙な光は、触れるものすべてを変化させました。空の箱を石の階段に。弾薬棚を羽毛ベッドに。保管庫の壁の一部を、驚いたイカでいっぱいの紫色の液体の間欠泉に。そして、なかには簡単に説明できないような何かに変わったものもありました。見慣れたものや変わったものが同化して、醜いものに姿を変えたのです。
すぐに、保管庫は収拾がつかないほどになりました。それでも二人のいじわる顔はそんなことは全然気にしません。自分たちが生み出した奇妙なものを見て、獣のような嫌な声を立てて笑っています。
しかしそのあと、ストライダーのコンテナに閉じ込められていたグラビットの幼体に光を当てて真鍮の便器に変えたとき、二人の楽しみは「とっても悪い考え」に変わったのです。
「みんな私たちのことが嫌いなのよ」と片方がささやきます。
「私だってあんな人たちのこと好きじゃないもん」ともう一人がにやりと笑いました。
「しなきゃいけないことや、しちゃいけないことを私たちに命令して楽しんでるのよ」
「偉そうにしちゃってさ。お腹の調子が悪くなっちゃいそう」
「みんなツイてるわね。私たちがちょうど、威張りん坊に効く薬を見つけてあげたんだもん」
二人は邪悪な微笑みを浮かべると、その箱を持って住宅区画のほうへとこっそり向かいました。まず二人は眠っている魚屋のところに行き、魚屋の両目を光るキノコに変えました。次に眠っているサイファーの校長のもとへ向かい、ベッドのシーツを火のついた丸太に変えました。その後は市場に向かい、区画全体を大きく渦巻く海水に変えました。店や商品がすべて、底なしの黒い海水に飲み込まれていきます。
そしてセンチネル・キャプテンの家に着くと、キャプテンの犬を半分がカメで半分がソーリアンの姿をした生き物に変えました。その生き物はその夜のうちに死んでしまいました。
それから二人はいちばん高い胸壁に青白いお尻をつけて座り、自分たちの成果に満足して獣のような嫌な声を立てて笑いました。魚屋の奥さんはおびえて泣き、サイファーの校長の家ではごうごうと火が燃え、中央市場では大騒ぎが起きています。
しかしやがて、二人のいじわる顔の少女らは笑うのをやめ、信じられない思いでただ目をこらしました。
「もうおしおきはじゅうぶんかな?」一人が思い切って言いました。
「残りは明日でもいいしね」もう一人が弱々しく笑顔を浮かべて言います。
「そうしたほうがいいわ。うん」
そんなわけで、自分たちのしたことを全部もとどおりにするために、二人は箱を街の方へ向けてパズルをもとの形にしようとしました。
しかしいくら思い通りにしようとしても、パズルはどんどん違う形になってしまいます。ひねったりひっくり返したりするたびに、街は恐ろしく変貌し始めました。最初に住宅区画が盛り上がり、折りたたまれたかと思うとフリーランサーのギルドハウスになってしまいました。次に、センチネルのオフィスが学校の先生の髪の毛のように編み込まれてしまいました。市場の嵐は周りを切り刻む金属の竜巻となって、鋭い音を立てながら家を引き裂いていきます。離れたところから、住民たちの叫び声が少女らの耳にまで届きました。
恐怖がどんどん膨らむなか、二人はひねったりひっくり返したり、回したり押したり、並び替えたり位置を戻したりしました。そうこうするうちに、目の前の世界が崩壊を始めました。街が建っている台地全体が裂けてばらばらになり、空中に投げ出されました。山は空に向かって崩れていきました。太陽は細い線になり、地平線のあたりに絡みつきました。
二人はぐちゃぐちゃになったもの——二人が唯一知る故郷と呼べる場所だったもの——に囲まれながら箱にしがみつき、空中へと持ち上げられました。少しの間、その場には大混乱しかありませんでした。二人にはお互いの叫び声しか聞こえません。
そして、二人は保管庫の床へとたたきつけられました。
辺りを見回すと、何一つ変わっていません。すべてが、以前と同じようにそこにありました。そして、例の箱は不吉に湯気を立てながら二人の間に舞い降りて、地面に触れたとたん一方向に転がりました。
顔に涙のあとを幾筋もつけて、片方が相手の方を向いて言いました。「もしかすると…もしかするとだけど、変わったものには触らないほうがいいのかもしれないわ。大人たちが言ってたみたいに」
「そうね」ともう一人がささやきます。「大人たちが言ってたみたいに。何度も何度もね」
その瞬間、キャプテンの気配を感じ取り、二人はいぶかしみました。
そして保管庫へのドアが壊されたかと思うと、センチネル・キャプテンと身体の大きな衛兵たち3人が大急ぎで駆けこんできました。
落ちた場所に横たわったままの少女と、二人の間に転がる箱を見たキャプテンは、腕を組み、かなり腹を立てている様子でした。
包帯を巻いて痛々しい様子の猟犬が見張っているなか、キャプテンは少女らをさらし台に固定し、人々の前へとさらしました。心の傷や恐怖を刻みこまれた住民たちは、法にのっとって、いじわる顔の少女らの指を3本ずつ切り落とすべきだと主張しました。
しかしセンチネル・キャプテンは眉をひそめ、冷たい声で言いました。「私は皆の期待を裏切った。このいじわる顔の子供たちを好きだという気持ちから、二人をかばってしまった。私たちは常に全力で…いえ、それ以上の力で、自分たちの生活を守るために取り組まなくてはならないのだわ。それが法律の条文とはいかなくとも、法の趣旨だから」それからキャプテンはその奇妙な箱を子供たちの方に向け、いじわるな顔を身の毛もよだつような恐ろしい顔に変えました。
一人目の顔からは、骨のような突起物がいくつも出てきました。突起物の間からは、ごわごわとした房状の黒い毛がとぐろを巻いたように生えています。両目は青白色に変わり、剥けた皮膚からはぶつぶつだらけで土色の肌が新たに現れました。もう一人はそれよりもひどい見た目です。片目と口の位置が入れ替わり、ほっぺたにはくねくねと動く巻きひげが生えているうえ、声はスプーンで錆びた金属をこすったときのよう。
子供たちが哀れなうめき声で泣きわめくなか、センチネル・キャプテンは静まり返った人々の方を向いて奇妙な箱を掲げました。
「決して、変わったものには、手を触れないように」
住民たちはうなずいて返事をしました。
それからというもの、恐ろしい顔をした二人の少女らは見るに耐えられるものではありませんでした。この容貌のせいで二人は出会うすべての人たちに怖がられ、敬遠されて、死ぬまでずっと二人ぼっちで暮らしたのでした。
Mary Kirby、Cathleen Rootsaert、Jay Watamaniuk に感謝を込めて。